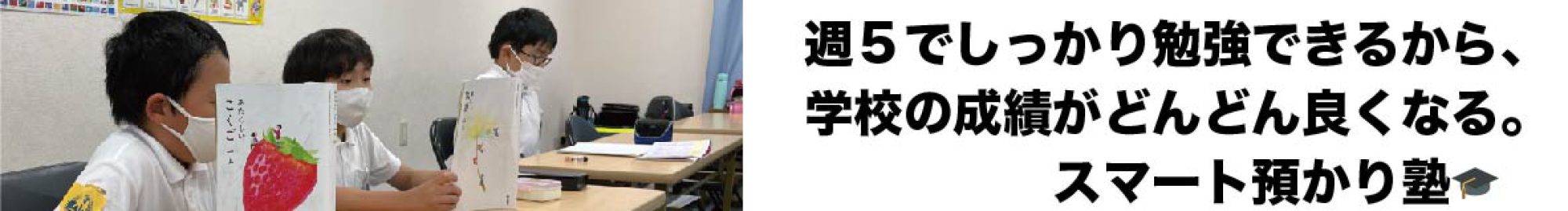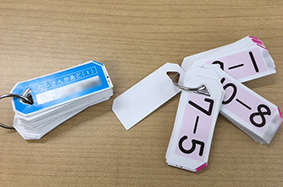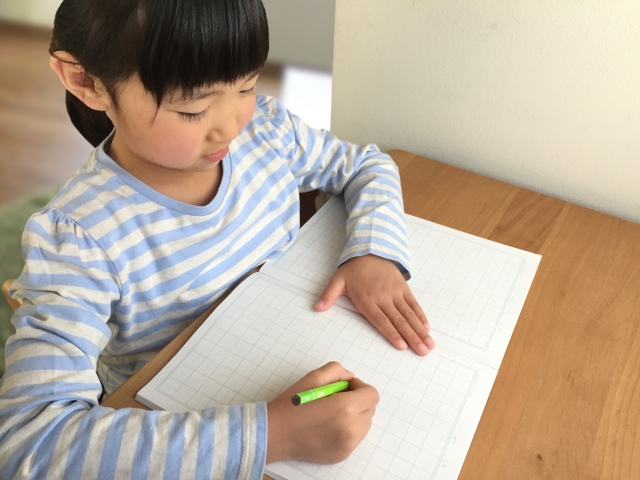この前、ひらがなの勉強が最優先という記事を書きました。
たくさんの人にご覧頂けたようです。
ありがとうございます。
夏休みが終わり、小学1年生の2学期からは、カタカナと漢字が出てきます。
スマートキッズに通っている1年生は、夏休みの間に、カタカナの読みが9割5分、書きが8割できるようになりました。
本格的にカタカナに取り組んでいた期間は、10日間程度です。
最初は、何が何だか分からないほぼ0(ゼロ)の状態でした。
カタカナを身につけた流れ
1:市販のカタカナ練習帳を1冊用意して、取り組む。
☆書店で販売している単語を中心とした練習帳です。ひらがなのふり仮名が付いているタイプが良いです。
ほぼ初めてカタカナに取り組むので、そのつど読み方を教えていきます。
2:練習帳が終了したら、練習帳の中の単語(食べ物、乗り物等)をノートに書き写し、読む。
☆書き写す回数は1回で構いません。何ページまでを書き写すか決めて、取り組みます。書き写しが終わったら1つずつ単語を読み上げてもらいます。
サマースクールは45分勉強15分休憩でしたので、1度に20語くらい練習して、1日に4時間程度やっていました。
3:⑵の書き写しを数日間やったら、カタカナでア行〜ワ行まで、書き出しテストをする。
☆書き終わったら○付けをします。間違った文字を見直し、文字の形を一緒に再確認します。間違いの多い行は、その行を練習帳に2回練習します。ナ行が苦手になりやすいようでした。
4:後日、カタカナの五十音表を10分間見せた後に、テストを実施する。
☆書き終わったら○付けをします。間違いのあった行は、練習帳に1回練習します。
テスト3回目で8割書けるようになりました。
カタカナをスムーズに覚えられたのは、ひらがなを先に身に付けられていた事が大きいと思います。
また、五十音の書き出しテストをすると、緊張感を持って取り組めるのでオススメですし、具体的にどの字が苦手なのか明確にわかります。
お家でも出来ると思いますので、取り組んでみてください。